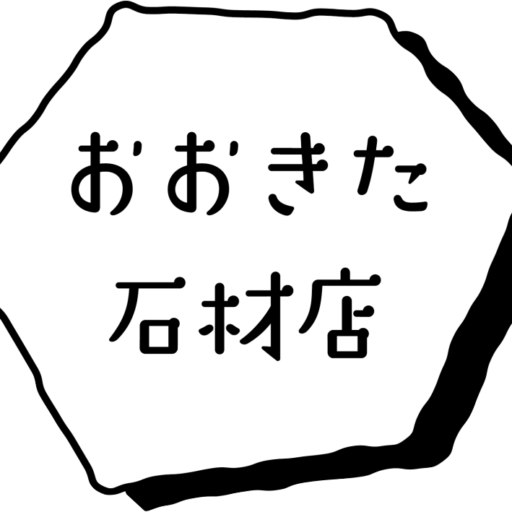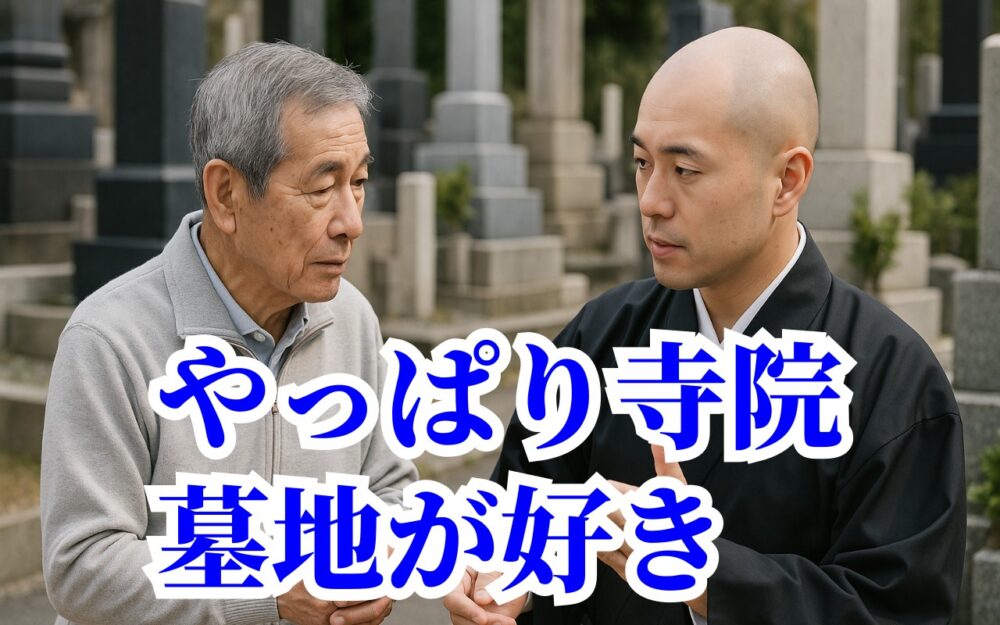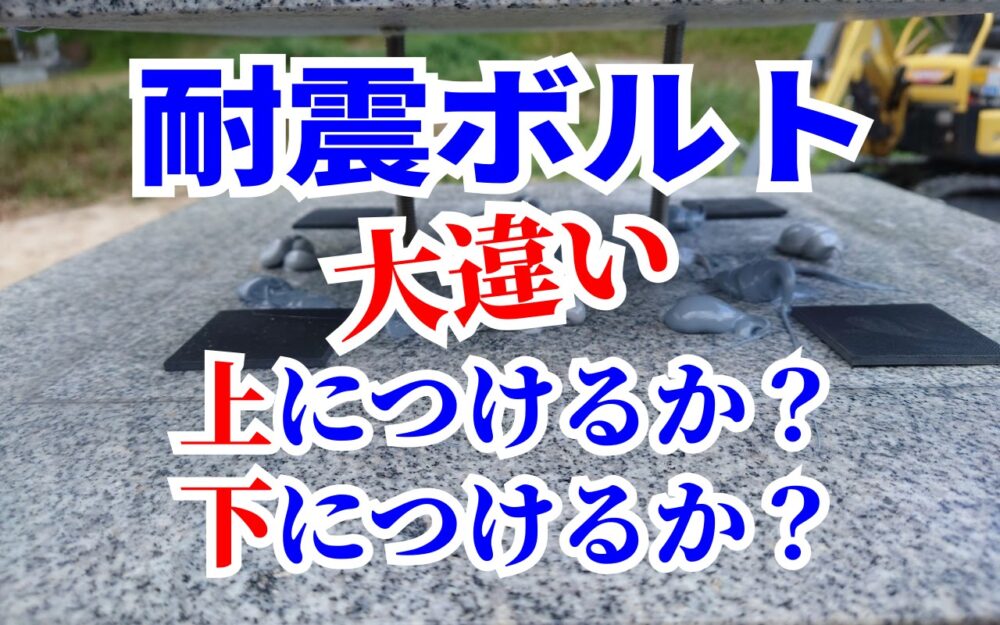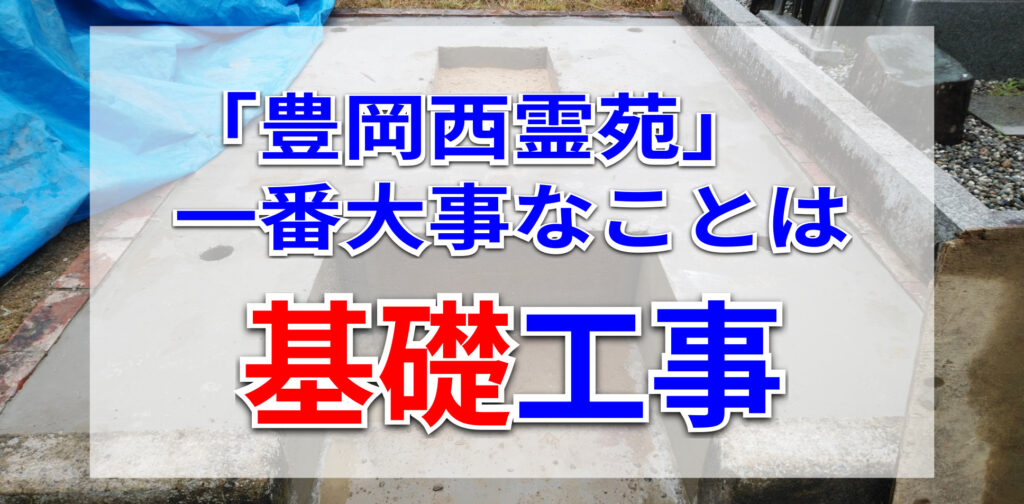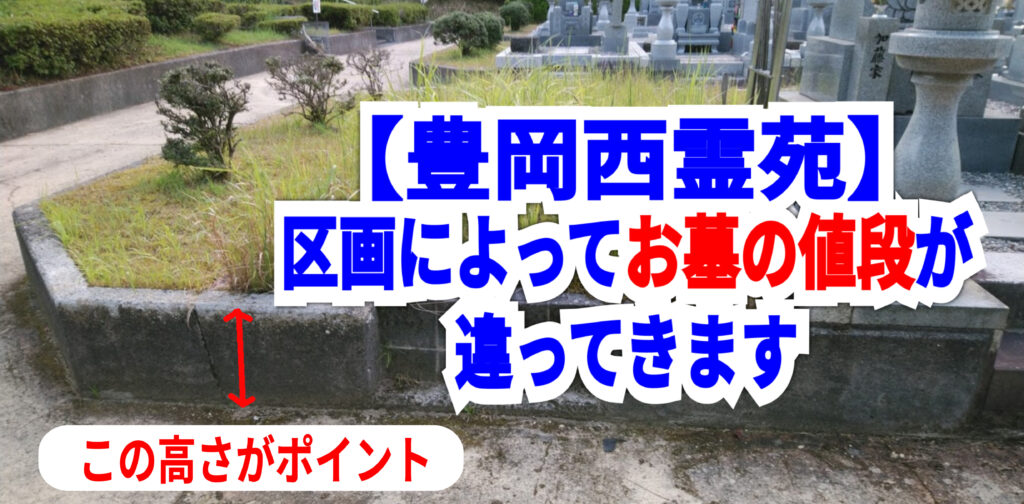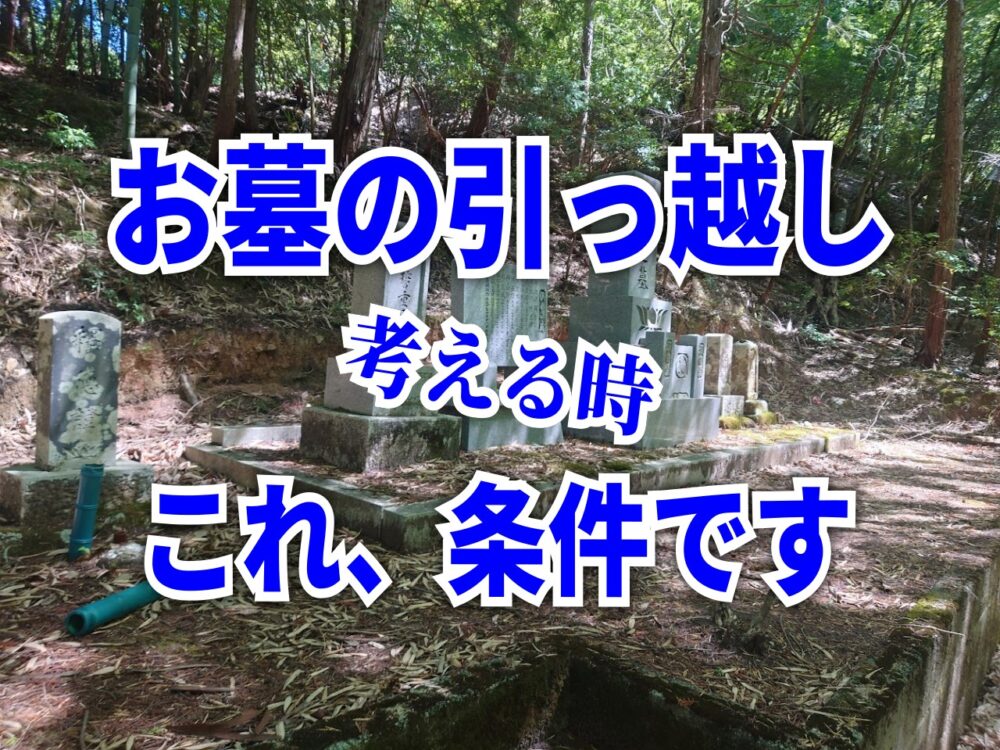「百年後に残るお墓」ってどんなお墓だろう。
構造がしっかりしているお墓でなくてはならない。
地震にも耐える、天災にもビクともしないお墓でなくてはならない。
雨漏りするお墓では、無理だろう。
飽きの来るデザインでは、百年後は残らないだろう。
そして、何よりも
お墓参りする人にとって、大切なお墓でないと、そもそも残りはしない。
そんなことを自問自答しながら、お墓を建てています。
「百年後に残るお墓」って、どんな素敵なお墓だろうか。
おおきた石材店 店主 大北 和彦